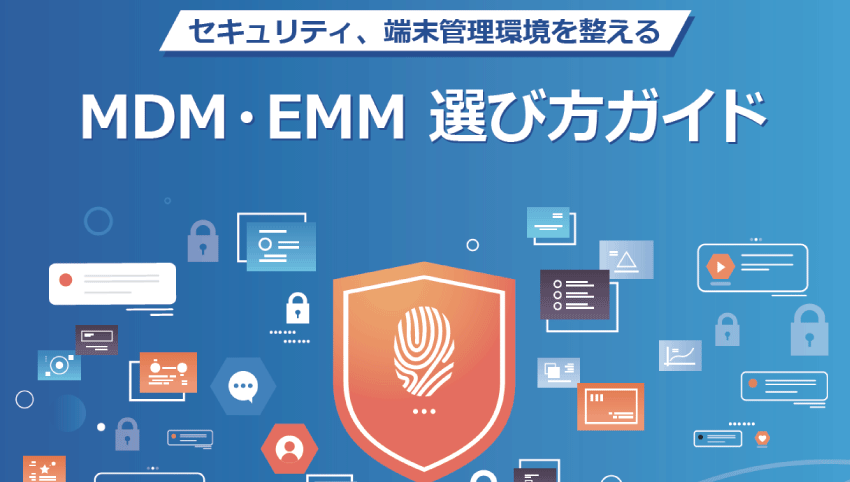業務の標準化はどうすれば良い?重要性や進めるコツについて

企業には様々な業務がありますが、社内のオペレーションマニュアルなどでルール化されているものもあれば、個人のやり方で運用されている属人的なものもあります。企業としては、後者の属人的な業務を解消し、生産性や効率化を進めたいところでしょう。
本記事では、業務標準化のメリットや具体的な進め方、進める際の注意点などについて解説します。
目次[非表示]
- 1.業務標準化とは?
- 2.業務標準化のメリット
- 2.1.業務の属人化が解消される
- 2.2.社内のナレッジが蓄積できる
- 2.3.業務成果が可視化される
- 2.4.商品の品質向上につながる
- 3.業務標準化の進め方
- 3.1.現状把握
- 3.2.標準化する業務の優先度を決定
- 3.3.タスクのマニュアル化とフローの整理
- 3.4.トラブル対応マニュアルの作成
- 3.5.PDCAを回す
- 4.標準化を進めるにあたっての注意点
- 4.1.業務標準化の目的を浸透させる
- 4.2.手段と目的を混同しない
- 4.3.定期的な見直しを行う
- 5.業務の標準化に活用できる「Unifinity」
- 6.デジタルツールを活用して業務標準化を効率的に進めよう
業務標準化とは?

「業務標準化」と一言で言っても、そこには「タスクの標準化」と「フローの標準化」という2つのアプローチがあります。
■合わせて読みたいページ
タスクの標準化
タスクの標準化とは、「誰が行っても均一の品質が保たれている状態」にすることです。会社には様々な従業員がいることから、当然ながら仕事のアウトプットの質にもばらつきが生じます。
個性を重視するクリエイティブな業務であれば、そのばらつきは差別化の源泉になりますが、そうではない場合は標準化を進め、誰が行っても同一のアウトプットがなされるような仕組みづくりが重要です。
フローの標準化
もう一つのフローの標準化とは、「誰でも業務を回せる状態」にすることです。業務内容が誰でもわかる状態になっていないと、異動や退職、休職など従業員が入れ替わったり抜けたりするタイミングで、現場の運用が混乱してしまいます。
誰が抜けても大きな支障なく業務にあたれる状態にしておくことが重要です。
業務標準化のメリット

業務標準化を進めることで、次にあげるようなメリットを享受できます。
業務の属人化が解消される
タスクやフローの標準化を進めることで業務の属人化を解消できます。属人化していると、業務がブラックボックス化してしまい限られた人しか対応できなくなるため、生産性が落ちたりトラブルへの対応が遅れたりと様々な観点でネガティブな影響が予測されるため、速やかな対応が必要です。
社内のナレッジが蓄積できる
業務標準化にあたり手順やマニュアルが整備されると、会社としてナレッジの蓄積がなされるようになります。ナレッジの蓄積により、該当業務の効率化が実現でき、メンバーはより重要な業務へと時間が割けるようになるでしょう。
業務成果が可視化される
業務が標準化されると、業務内容が社内で可視化されるため、誰がいつまでにどのような目標に向かって何の業務を行えば良いかが明確になります。達成すべき成果が定量的に把握できるため、そのための道筋も見えやすく、従業員のモチベーション向上にもつながりやすくなります。
商品の品質向上につながる
業務が標準化されると担当者ごとのばらつきが是正されるため、顧客へ提供される商品やサービスの品質も安定・向上します。結果的に売上増加にもつながりやすくなるでしょう。
業務標準化の進め方

次に、業務標準化の進め方について、以下の流れに沿って解説します。
現状把握
まずは現在、どのような業務が社内で行われているのか、現状把握を進めましょう。具体的には、実際に従業員などへのヒアリングを行い、業務フローをチェックして、必要に応じて記入されている資料やPCに入力されているデータ内容もチェックします。
ポイントは、タスクレベルで可能な限りMECE(もれなく、ダブりなく)に洗い出すことです。もしもその過程で、ヒアリングしても内容が明瞭にならない業務や、誰が対応しているのか判然としない業務などがあれば、そこが標準化の対象候補となるでしょう。
標準化する業務の優先度を決定
現場で行われている業務のヒアリングと現状把握が完了したら、そこから標準化の対象となる業務を抽出し、優先順位をつけます。該当業務が停止した場合の社内へのインパクトを考えたうえで、優先順位を割り振ることがポイントです。
タスクのマニュアル化とフローの整理
標準化を進める業務が決定したら、タスクレベルで作業内容を明文化し、誰が実施しても対応可能なように業務内容を最適化しましょう。そのうえで、内容をマニュアルとして整備することで、人を選ばずいつでも業務内容をキャッチアップできるようになります。
もちろん、タスク内容だけを明記するのではなく、どのようなフローで業務が流れていくかの整理もあわせて行い、担当者間や部署間での連携に支障が出ないようにすることも大切です。
トラブル対応マニュアルの作成
通常の業務フローのマニュアルを作成するだけでは完璧な標準化とは言えません。イレギュラーな事態が発生した際の対応についても、誰がどのような対応をするかオペレーションを明確にしマニュアルに記載しておきます。
トラブル対応マニュアルを作成することで、有事の際にも混乱なく対応できるでしょう。
PDCAを回す
各種マニュアル整備を終えておしまいではなく、PDCAを回して定期的にその内容を改善していくことが大切です。
マニュアルを作っても、いざ現場で実践してみると想定とは違いうまく業務が回らないことは多々あります。そうなるとマニュアルの意義そのものが失われてしまい、属人的なオペレーションが再発してしまう可能性も考えられます。
そのような事態を避けるためにも、マニュアルと実際の運用の間に齟齬がないか、新たに標準化が必要な業務がないかなどを定期的に従業員へヒアリングし、必要に応じてマニュアルを更新していきましょう。
標準化を進めるにあたっての注意点

ここまでは業務標準化の進め方についてお伝えしましたが、これらを実践するに当たっては、注意点もあります。
業務標準化の目的を浸透させる
業務標準化を進めるにあたっては、事前に従業員に対して、その目的をしっかりと共有して浸透させるようにしましょう。目的の理解を促さないままで標準化を進めようとすると、思わぬところでつまずいてしまう可能性があります。
標準化の対象はあくまで業務を実行する現場にあることを念頭に、従業員への目的の浸透をおろそかにしないよう意識しましょう。
手段と目的を混同しない
業務標準化=マニュアル作成と考える方も少なくありません。しかし、マニュアルはあくまで目的に対する一つのアウトプットです。
マニュアルを作りきることが目的となってしまわないよう注意しながら進めましょう。
定期的な見直しを行う
作成したマニュアルは定期的に見直しましょう。長年更新されないマニュアルは形骸化しやすく、結果的に属人化の温床となります。業務標準化プロジェクトのPDCAをしっかりと回すように心がけましょう。
業務の標準化に活用できる「Unifinity」

業務標準化のアウトプットとして重要な役割を担うマニュアル作成ですが、あらゆる業務におけるDXが加速する昨今においては、マニュアルのデジタル化も重要なテーマとなります。
たとえば「Unifinity」は、複雑なコードや開発が不要で簡単にアプリを作成できるサービスです。パワーポイントのような感覚で直感的な操作が可能なほか、作成したアプリは審査不要ですぐに運用できます。
Unifinityにマニュアルをアップロードすれば、従業員のモバイル端末から簡単にマニュアルの閲覧が可能です。更新のたびに印刷する手間やマニュアルの所在がわからなくなる心配も不要です。
また、アプリを作成すれば点検報告や在庫管理、資産管理など様々な業務がモバイル端末で行えるようになるため、マニュアル確認後の実務への移行もシームレスに行えます。
このようなツールを導入することも、業務標準化を進める重要な取り組みです。
ツール詳細:Unifinity
デジタルツールを活用して業務標準化を効率的に進めよう
業務標準化の最終目的は、属人化の解消や業務効率アップにあります。そのためのアウトプットの一つとしてマニュアル作成がありますが、大事なことはそれ自体が目的にならないように注意することです。
マニュアル作成を一からはじめるのは大変な労力です。ぜひ本記事でご紹介したようなデジタルツールを活用して、社内全体の業務標準化を効率的に進めるようにしましょう。
自社の業務標準化をお考えの方は、ぜひお気軽にコネクシオまでご相談ください。
関連記事:中小企業の営業改革にSalesforceは必須!メリットと事例を解説
■合わせて読みたいページ