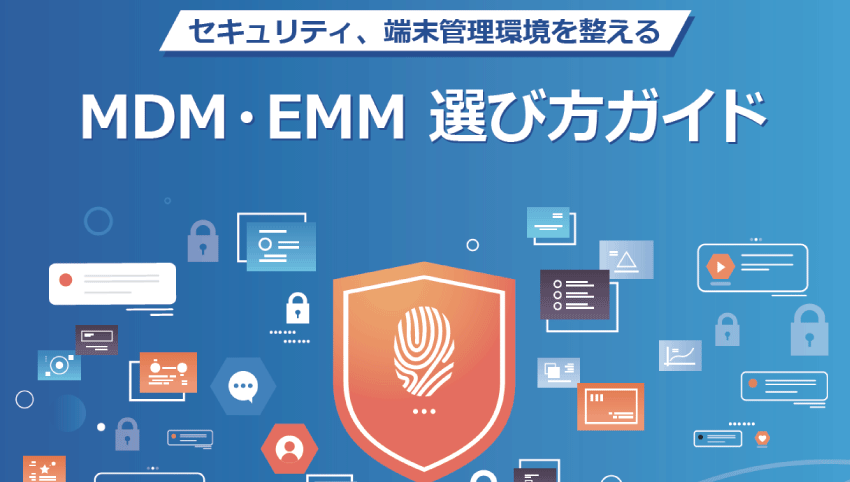「新しい働き方」とは? 具体事例、推進のためのポイントを解説

コロナ禍をきっかけとして、働き方という観点で構造的な変革が起こっています。
世界的にテレワークが普及しましたが、その一方で在宅勤務を禁止したテスラを筆頭に、Googleやホンダ、東芝など、在宅勤務の縮小の動きも加速しています。日本においては、これに加えて働き手の減少など人口構造の変化も進んでおり、既存のワークスタイルだけでは社会を維持するのが難しくなってきています。
そんな環境が著しく変動するVUCAな時代において、「新しい働き方」は民間のみならず、政府も含めた国家全体の課題だと言えます。
今回は、昨今何かと話題になっている新しい働き方について、様々な制度を軸に解説します。
目次[非表示]
- 1.新しい働き方が求められる背景
- 1.1.日本政府が打ち出すSociety5.0
- 1.2.DXの浸透による働き方の変化
- 1.3.withコロナ時代の持続可能な働き方
- 2.新しい働き方の打ち手・事例
- 3.いつでもどこでも多様に働けることが重要
- 3.1.生産性向上と業務効率
- 3.2.ワークライフバランスの確保
- 3.3.ICT環境とセキュリティの確保
- 4.働き方の正解は企業によって千差万別
新しい働き方が求められる背景

まずは新しい働き方が求められる背景について、政府軸と民間軸、それから環境軸でそれぞれ説明します。
日本政府が打ち出すSociety5.0
新しい働き方が求められる背景の大きな要因の一つとして、政府が掲げるSociety 5.0の存在があります。
Society 5.0とは、2016年1月に閣議決定された「第5期科学技術基本計画」のなかで提示された次世代の社会システムの概念です。内閣府のページでは「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」と説明されています。
このような、デジタルファーストなSociety 5.0の社会で活躍できる人材、すなわち技術革新に対応して新たな価値を創出できる人材を育成するためにも、新しい働き方が求められていると言えます。
DXの浸透による働き方の変化
一方で民間に目を向けてみると、DX(デジタルトランスフォーメーション)の浸透が働き方の変化を後押ししています。
そもそもDXが求められている背景には様々な要因が考えられますが、前述のSociety 5.0の存在をはじめ、生産年齢人口と労働力人口の減少に伴う生産性の向上や、コロナ禍における強制的なデジタル化への対応、そして経済産業省による「DXレポート」などが挙げられるでしょう。
「DXレポート」とは2018年秋に経済産業省から発表されたもの。企業がレガシーシステムを使い続けた場合、2025年以降のシステムの保守・運用費が膨大になり、現在の約3倍となる最大12兆円/年の経済損失が生じる危険性があることが指摘されました。
これを見た企業経営者が、相次いでDXを具体的に進めることになりました。
DXは、何か一部のシステムを導入したり入れ替えたりすれば達成するものではなく、企業という組織体そのものも含めて構造的に変革する必要がある取り組みです。よって、それにフィットする新しい働き方のデザインも必須になるというわけです。
関連記事:DXやIT活用と生産性向上の関係とは? 指標とともに解説
withコロナ時代の持続可能な働き方
環境軸で考えてみると、先述した新型コロナウイルスのパンデミックが大きなトピックとしてあげられます。
ウィズコロナの現在、多くの企業がテレワークを導入することになりました。それに併せて課題も浮き彫りになり、多種多様な働き方について各企業が模索し始めている状況だと言えます。
冒頭にお伝えしたテスラやGoogle、ホンダ、東芝などは、テレワークの実践を経て対面による働き方の価値を再認識した上で、在宅勤務の縮小を選択したと言えます。
テスラ CEOのイーロン・マスク氏は幹部向けメールで「在宅勤務希望者は、最低40時間/週のオフィス勤務が必要だ。さもなくばテスラを退社してもらう」と命じています。また、Googleは2022年4月から週3日以上のオフィス勤務を促しており、ホンダは2022年5月から従来型の週5日オフィス勤務に戻しています。
つまり各社とも、持続可能な働き方に向けた模索を続けていると言えます。
関連資料:会社の実情に合うのはどれ?テレワーク環境の選び方について、タイプ別に解説
■合わせて読みたいページ
新しい働き方の打ち手・事例

次に、具体的な新しい働き方について、以下7つの打ち手や事例を解説します。
ハイブリッドワーク
ハイブリッドワークとは、従来型のオフィスワークとテレワークを組み合わせた働き方です。
ハイブリットワークを導入することで全てのメンバーをオフィスに集める必要がなくなるので、企業としてはオフィス空間の省力化や小規模化を実現し、コスト削減や空間の有効活用を推進できます。
また従業員としては、働き方が柔軟になる分ワークライフバランスを実現しやすくなるので、従業員満足度の向上も期待できるでしょう。
関連記事:ハイブリッドワークとは? 新しい働き方を実現するための注意点・ポイントを解説
ABW
ABWとは “Activity Based Working” の頭文字をつなげた造語で、時間や場所に縛られずに働けるワークスタイルを指す言葉です。
ハイブリッドワークが、在宅や外出先など働く「場所」をある程度自由に選べる制度を指すのに対して、ABWは場所のみならず時間も含めて社内外問わず、働く人の活動に応じて好きな形で働ける制度となります。
各活動に最適化された場が用意されることになるので、従業員満足度の向上はもちろん、生産性の向上にも寄与するでしょう。また、様々な形での就業を可能とすることから不測の事態にも対応しやすく、事業全体がサステナブルな形へと昇華することが期待できます。
関連記事:持続可能な働き方ABWとは? 概念や定義、メリットを解説
ワーケーション
ワーケーションとは「ワーク+バケーション」の造語で、場所にとらわれずに働くことを指します。多くの文脈では、普段とは異なる地域にいながら仕事を進めることを指しますが、そのほかにも、会社の地域進出を促進するためのワーケーションや、地域にとっての移住・定住のためのワーケーションなど、様々な類型が存在します。
ワーケーションも、先述したハイブリッドワークやABWと同様に生産性向上や従業員満足度の向上に寄与するだけでなく、一般的に知れ渡った用語だからこそ採用力の向上にも繋がることが期待されます。
週休3日
ここ数年で大企業を中心に流行っているのが「週休3日」です。
日立製作所やパナソニックホールディングスなどの大手電機メーカーは2022年度中に週休3日を選べる制度の導入を検討していますし、大手製薬企業の塩野義製薬は2022年4月より、社員が週休3日を選べる制度を開始しています。
従業員にとっては自由時間の拡大につながりますし、働きながら育児や介護にも対応しやすくなります。また企業にとっても、優秀な人材確保や離職の防止などを期待することができるでしょう。

副業・兼業
副業とは、メインである本業を疎かにしない範囲で他社の業務も行うことです。また兼業とは、本業以外の事業を2つ以上並行して対応・担当することです。
特に前者の副業は、多くの企業で解禁の流れが活発化しています。
従業員にとっては、収入の増加や新しい知識・スキルの習得がしやすくなります。また企業にとっては、従業員のスキルアップはもちろん、自由度が高いという観点で優秀な人材確保に向けたPRにも使うことができます。
バーチャルオフィス(仮想オフィス)
これからの時代、働く場所は現実空間だけではありません。昨今ではテクノロジーの発達によって、バーチャル空間での就業も少しずつ可能になってきています。
具体的には、VRグラスを装着してバーチャル空間上に存在するオフィス(バーチャルオフィス)へと仮想出社する方法があります。2022年は特にメタバースが大きな話題になったこともあり、このバーチャルオフィスも注目されることになりました。
Zoomなどの2次元のオンライン会議システムでは実現が難しい、対面ライクなコミュニケーションの実現に期待が高まっていますが、現時点ではまだデバイスの普及や通信速度等の課題も相まって、社会実装が進んでいるとは言えません。
中長期的に実現するであろう手法として捉えていただければと思います。
企業独自の休暇制度
最後は、企業独自の休暇制度の存在です。
たとえば、エクステリアや外構空間の商品販売を行う株式会社デジアラホールディングスでは、2008年より「親孝行休暇」という制度を導入しています。これは年に1度取得できるもので、名前のとおり、従業員による親孝行を促進するために設けられた休暇制度となります。
関連記事:デジアラホールディングスの福利厚生
このようなユニークな休暇制度を設けることで、企業としての採用等のPRにつながるのはもちろん、従業員満足度の向上にも寄与します。
いつでもどこでも多様に働けることが重要

ここまでの内容をまとめると、以下の3点が新しい働き方のメリットであり期待される効果だと言えます。
生産性向上と業務効率
多様な働き方ができるように整備すると、結果として生産性の向上や業務効率化に寄与します。その際に、成果を評価制度に組み込むことが大切です。成果を適切に評価する制度があることで、生産性の向上や業務効率化へのモチベーションも向上すると言えます。
ワークライフバランスの確保
新しい働き方が浸透すると、従業員のワークライフバランスの確保にもつながります。ハイブリッドワークやABW、週休3日が実現することで、従業員は自身の時間をより多く確保しやすくなり、プライベートを充実させたり、介護や子育て等により多くの時間を割けたりできるようになるでしょう。
ICT環境とセキュリティの確保
なお、これらのメリットを享受するためには、適切なICT環境とセキュリティの確保が必要となります。オフィス勤務前提ではなくなるので、その分従業員に貸与するデバイス等のICT機器の内容も変わるでしょうし、インストールするソフトや利用するクラウドサービスも変わってくるでしょう。
さらに、シャドーIT等のリスクにも対応できるようなセキュリティの構築も必要です。セキュリティ対策を怠ると、致命的なセキュリティ事故につながりかねないので、十分に注意してください。
関連記事:管理職を悩ませるシャドーITとは?取り組むべき課題と対策
働き方の正解は企業によって千差万別
今回は「新しい働き方」という切り口で、様々な打ち手や事例を紹介していきました。働き方は企業によって正解が異なるので、自社にフィットする働き方や場のあり方は千差万別だと言えます。
自社が置かれた環境に鑑みて、適切な打ち手を導入するように検討を進めていきましょう。
■合わせて読みたいページ