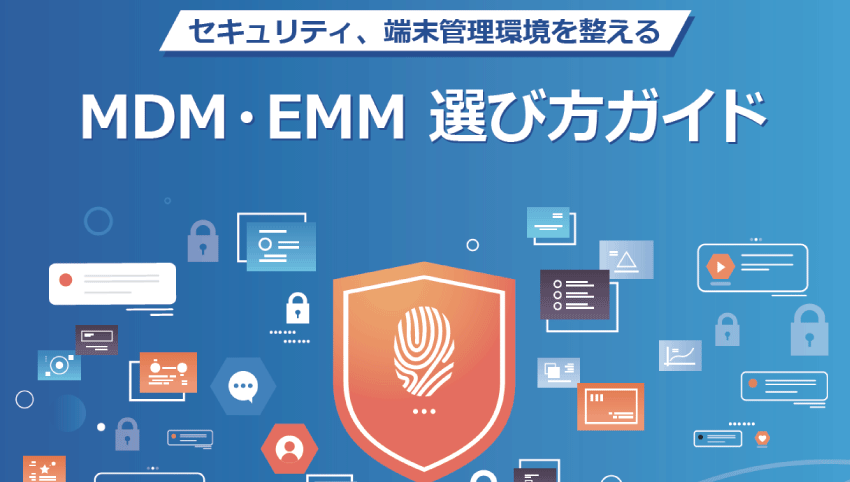アルコールチェック義務化はいつから?知っておきたいポイントと対策を解説

道路交通法の改正に伴い、2022年4月から実施が予定されていたアルコールチェック義務化が、新型コロナウイルス感染症の影響により延期となりました。現在のところ、実施時期は未定です。しかしいつかは実施されることは確実です。アルコールチェックを導入する企業としては、導入前に必要事項を確認しておく必要があるでしょう。本記事では、アルコールチェック義務化とは何か、導入を検討している企業に必要なポイントや対策などを解説します。
目次[非表示]
アルコールチェックの義務化とは

アルコールチェック義務化は、2022年4月施行の道路交通法の改正によるものです。これにより、白ナンバー事業者においても、安全運転管理者による運転前後の従業員に対する目視でのアルコールチェック業務が義務になりました。2022年10月からは検知器を使用したアルコールチェックが義務化されていましたが、こちらは延期されています。これまでも緑ナンバー車両ではアルコールチェックが義務化されていましたが、白ナンバー車両にもアルコールチェックが必要になります。
緑ナンバーとは、他社の人員や荷物を、有償で運ぶ事業用車両のことで、タクシーやトラックなどが該当します。また白ナンバーとは、自社の人員や荷物を無償で運ぶ車両で、社用車や配送用車両のことを指します。
アルコールチェック義務化拡大の背景
アルコールチェック義務化が白ナンバーにまで拡大した背景には、2021年の千葉県八街市での事故があります。飲酒運転のトラックに下校中の児童5人がはねられ、死傷した事故です。
このトラックは白ナンバーの車両だったため、アルコールチェックはされていなかったのが、事故の原因の1つと考えられています。そのため飲酒運転の厳罰化が進み、白ナンバー車両にもアルコールチェックが求められるようになりました。
アルコールチェック義務化拡大の概要
アルコールチェックの義務化は、2022年の道路交通法の改正により段階的に実施されています。
●2022年4月施行
白ナンバー事業者においても、運転前後の運転者のアルコールチェックを行います。確認は目視で行い、その記録は1年間保存しなくてはなりません。アルコールチェックと記録の保存は、安全運転管理者が行います。営業所が複数あっても、安全運転管理者がアルコールチェックを行う必要があります。
●2022年10月施行予定
目視ではなく、アルコール検知器を使用したチェックを行います。それ以外は4月からの内容と同じです。ただし、現在こちらの施行は延期されており、施行予定は未定です。
アルコールチェック義務化の対象
アルコールチェックが義務化されているのは、次のいずれかの条件を満たす企業です。
●自動車5台以上の所有
※自動二輪車(50cc以下の原付は除く)は1台を0.5台として計算する。
●定員11人以上の自動車1台以上の所有
緑ナンバー車両と白ナンバー車両を合わせた台数が基準となります。車両の台数は、企業全体ではなく、事業所ごとに計算します。当てはまる企業は少なくないでしょう。
違反刑罰
違反行為には、次のような罰則があります。
●アルコールチェックを行わない場合
安全運転管理者の業務違反となります。現在罰則規定はありませんが、今後罰則が科される可能性があります。
●運転者が飲酒運転を行った場合
運転者だけでなく、場合によっては企業の代表者や運行管理責任者にも、事業停止や車両使用停止、免許取り消しなどの罰則が科される恐れがあります。
●安全運転管理者を選任していない場合
罰金5万円以下の罰則が発生します。
▼合わせてよく読まれている資料
アルコールチェック義務化による業務の変化
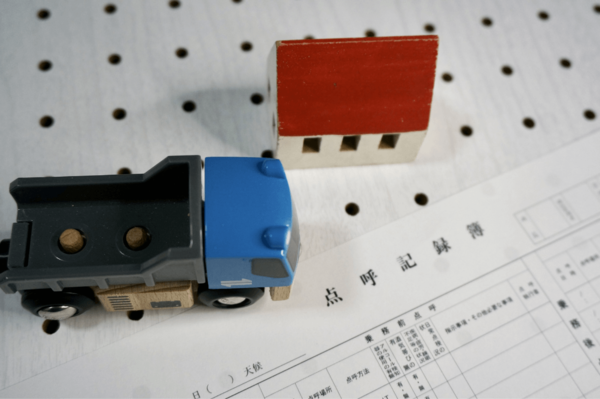
アルコールチェック義務化により、安全運転管理者の業務はどのように変化したのでしょうか。
道路交通法改正前の業務
2022年4月の道路交通法改正前は、安全運転管理者には次のような業務がありました。
●運転者の状況把握(健康状態など)
●運行計画の作成
●交替する運転者の確保・配置(長距離・夜間運転時など)
●異常気象時など必要に応じた安全確保
●始業時の点呼と車両の日常点検
●運転日誌の備え付け、および記録管理
●運転者への安全運転指導
2022年4月の道路交通法改正後に追加された業務
2022年4月の道路交通法改正後は、安全運転管理者には次のような業務が追加されています。
●運転前後の、運転者のアルコールチェック(目視またはアルコール検知器)
●アルコールチェックの記録の保存・管理
記録の方法・形式に決まりはありません。アナログでもデジタルでも大丈夫です。ただし、確認後1年間は保存しなくてはなりません。アルコール検知器によるチェックが始まれば、検知器の備え付けや管理、動作確認なども業務に含まれます。
アルコールチェック義務化に向けた準備

アルコールチェック義務化に対応するためには、各企業において次のような準備が必要です。
安全運転管理者の選定
アルコールチェックだけでなく、事業所の車両の安全運転に責任を持つ、安全運転管理者を選任しなくてはなりません。規定以上の車両を保有する事業所ごとに、安全運転管理者を1人選任し、15日以内に管轄の警察署へ届出を提出する必要があります。その後は年に一度、安全運転管理者等講習を受講します。
安全運転管理者には、次のような条件があります。
●20歳以上(副安全管理者を置く場合は30歳以上)
●運転管理の実務経験2年以上(公安委員会の講習を受けている場合は1年でも可)
●過去2年以内に違反行為をしていないこと
安全運転管理者の不在時に備え、副安全運転管理者を置くこともできます。
ドライバー、安全運転管理者への教育
運転者や安全運転管理者に、飲酒運転禁止についての教育を行います。「翌朝になったら大丈夫」「時間が経過したから大丈夫」などと考える運転者もいるので、飲酒運転についての徹底した教育が必要です。
また安全運転管理者には、飲酒運転があれば事業部や管理者へも影響することを伝え、業務を徹底するように促す必要があります。法定講習の受講も重要です。
アルコール検知器の導入
現在は延期されていますが、アルコール検知器によるチェックの実施を見据え、できるだけ早く検知器を導入する必要があります。また、アルコール検知器によるチェック、記録、記録の保管についての業務フローも決めておきましょう。
道路交通法では「国家公安委員会が定めるアルコール検知器を使うこと」と指定されていますが、アルコール検知器には法的な指定はありません。息を吹きかける方法で検査するもので、正常に動作し、結果がわかりやすいものであれば問題ありません。常に正常に動作するよう、適切に管理し、定期的に確認する必要があります。
しかし、毎日の記録を保存・管理することは大変です。特に運転者が日帰りではなく泊まりで移動している場合は、運転前後のアルコールチェックは運転者が行って結果を報告することが多くなります。
自動報告で業務負荷軽減
現在、多くの企業ではメールなどでアルコールチェックの結果を報告し、紙やExcelで記録・保存しています。安全運転管理者もチェックを実施する運転者も、これらの作業は負担が大きくなっています。
そこで導入をおすすめしたいのが、アルコールチェックの結果をクラウド管理できる「アルキラーPlus」です。アルコール検知器でのチェックの結果をクラウド保存できるソリューションです。正確な結果を容易に保存でき、安全運転管理者の業務が楽になります。
特にLINE WORKSと連携した「アルキラーPlus×LINE WORKS」では、アルキラーPlusがアルコールを検知すると、即座に安全運転管理者にメッセージが届き、速やかに対応できます。
リアルタイムで情報を取得できる、なりすましができないなどのアルキラーPlusのメリットに加えて、普段使い慣れたLINEで連絡ができるので気軽に使いこなすことができます。
準備は案外多いので早めに取りかかろう

アルコール検知器によるアルコールチェックの義務化がいつ実施されるかは、現在のところ未定です。しかし、実施されることは決定されています。安全運転管理者の選定や講習、業務フローの確立など、準備しなくてはならないことはたくさんあります。対象となる事業所では、できるだけ早く準備に取りかかりましょう。
なおコネクシオでは、LINEの使いやすさはそのままに、上記の【アルキラーPlus】のような外部アプリとの連携が可能なビジネスチャットツール「LINE WORKS」をご提供しています。
アルコールチェックの義務化について対策を検討されている方はぜひコネクシオにご相談ください。
▼合わせてよく読まれている資料
この記事を見た方へおすすめのサービス