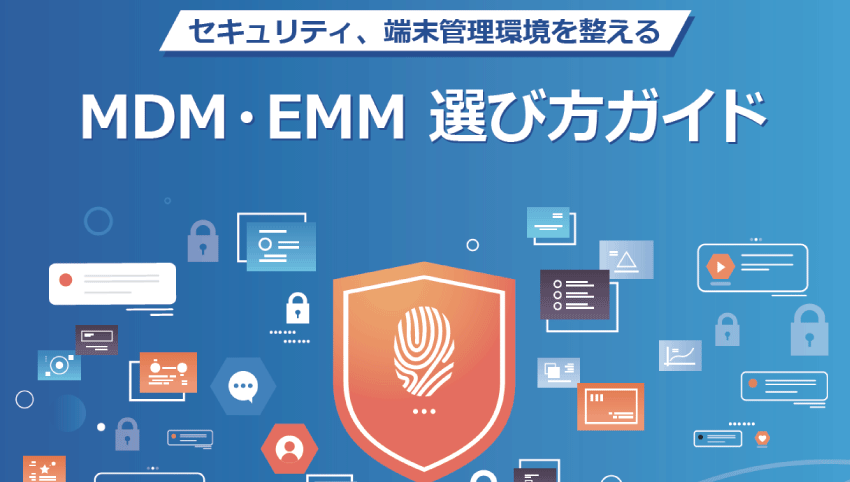テレワーク導入後の労務管理の課題と解決法

働き方改革、DX推進、新型コロナウイルスの感染拡大など様々な要因により、ワークスタイルはここ数年で激変しています。その中心的な勤務体系のひとつがテレワークです。
ICTを活用した在宅勤務などの場所や時間にとらわれない柔軟な働き方で、企業にも従業員にも大きなメリットがあります。一方でコロナ禍により制度が先行してしまった事例も多く、労務管理に課題を抱えている企業も多く存在します。
この記事では、テレワークにおける労務管理のポイントや注意点について紹介いたします。
目次[非表示]
- 1.テレワークのメリットとデメリット
- 1.1.テレワークのメリット
- 1.2.テレワークのデメリット
- 2.テレワークの労働時間について
- 3.テレワーク導入による給与・諸手当について
- 3.1.テレワークの費用負担について
- 3.1.1.1.機器の費用
- 3.1.2.2.通信回線費
- 3.1.3.3.電話に関わる費用
- 3.1.4.4.文具、備品、宅配便等の費用
- 3.1.5.5.水道光熱費
- 4.テレワークの人事評価制度について
- 5.従業員の意識改革も必要になる
- 6.連絡体制について
- 7.おわりに
テレワークのメリットとデメリット
テレワークは、Tel(離れて)とWork(仕事)を組み合わせた造語で、ICT技術を活用して、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を指します。テレワークには、スマホやタブレットを活用して社外で勤務するモバイル勤務(モバイルワーク)と、在宅勤務型に大別できます。
テレワークのメリット
すでに周知されていることではありますが、テレワークのメリットは柔軟な働き方が実現できるため、生産性の向上や多様な働き方の実現が可能となります。例えば、前者では営業マンが会議や資料作成のために出先からわざわざオフィスに戻る必要がなくなることで、移動時間の削減が可能になります。後者では、介護や育児などでフルタイム勤務が難しい場合でも、在宅勤務をすることで高い生産性とワークライフバランスを確保できます。
テレワークのデメリット
テレワークのデメリットは、すでにお伝えしている通り、労務管理の難しさが挙げられます。就業規則通りの時間を働いていないことも問題ですが、在宅勤務ではオンオフの境目が曖昧になることもあり、隠れ残業も発生しがちです。知らず知らずのうちに残業時間が増大し、健康やメンタルヘルスに失調をきたす例も多くなっています。
テレワーク下はでは、生産性の高い労働環境を実現することはもちろんのこと、過労も防止していく必要があり、従業員の健康を守るためにも適切な労働管理が求められています。
続いて、在宅勤務型について、労働基準法等の労働関係法令や人事労務管理上の注意点について解説します。
※下記資料もご参考にされることをお勧めいたします。
厚生労働省「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について」
■合わせて読みたいページ
テレワークの労働時間について
在宅勤務の場合、どのような方々がこのワークスタイルを活用しているかイメージしてください。代表的な例としては、介護や育児などが挙げられますし、コロナ禍の現在、多くの人がテレワークを活用しています。
テレワークには勤務時間の中に、介護や育児に係る時間やそれ以外の理由でも勤務とは別の日常生活時間が混在しています。そのため、事業所内勤務者の労働時間の管理方法と同様ですと、課題や齟齬が生じます。
多くの企業が出退勤管理を、メールでの管理、ビジネスチャットなど社内コミュニケーションツールでの報告、クラウド勤怠管理、PCの使用時間によるログ取得などで行われていますが、オフィスで働くように厳密に管理は難しいと言えるでしょう。
事業場外労働のみなし労働時間制の導入
テレワークの労務管理として有効な制度が「事業場外労働のみなし労働時間制」です。在宅勤務のように労働時間を算定しにくい働き方の場合、事業場外労働のみなし労働時間制(労働基準法第38条の2)を適用することができます。
みなし労働時間が適用されると、在宅勤務を行う従業員が就業規則などで定められた所定労働時間を勤務したものとみなされます。ただし、通常所定労働時間を超えて労働する時は、必要とされる時間労働したものとみなされます。労使の書面協定がある場合は、協定で定める時間が通常必要される時間とされ、その労使協定を労働基準監督所長へ届けが必要となります。
なお、みなし労働時間制を適用しても、法定労働時間を超えて労働させる場合、時間外労働に係る36協定(さぶろくきょうてい:労働基準法第36条)の締結と、届け出、及び割増賃金の支払が必要です。また、深夜労働の場合は割増賃金の支払が必要です。
具体的な管理方法としては、業務に従事した時間と内容を作業日報等で記録するなどにより労働時間と状況を把握します。また、始業・終業時に上司へのメールや電話で連絡するなどのルールを明確にすることが求められます。
テレワーク導入による給与・諸手当について
テレワークを導入しても業務内容や職種、勤務時間などの労働条件に変更がなければ、基本給の見直しは必要ありません。
ただし、育児や介護がテレワークの発生原因で、業務内容や職種が同様でも、所定労働時間の変更に応じての基本給の見直しは相当でしょう。
在宅勤務の場合、通勤の負担がない分、従業員は楽になりますが、これを理由として基本給の変更はできません。また、通勤手当の支給はなくなり、会議などの招集による臨時的な出退勤に関わる費用について実額支給となることが多いです。また在宅勤務で発生する電気代・通信費などは「在宅勤務手当」として支給している会社も多くです。事業所への出勤と在宅勤務の期間が時期により変動するようなケースでは、従業員の負担にならないようにしながら、定期の購入や実費支給を比較検討しましょう。
テレワークの費用負担について
事業所勤務の場合であれば、さして気にする必要のない、光熱費や通信費など、在宅勤務となるときちんとした線引きが必要になります。労働基準法第89条第5号では、「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項を就業規則に定めなければならない」とされています。取り決めが必要な項目としては主に以下の5つです。
1.機器の費用
パソコンやプリンター、スマホなどの機器については、会社からの貸与が多く見られます。
2.通信回線費
通信費用も会社負担のケースが多く見られます。自宅に引く回線の工事費、基本料金、通信回線使用料については、すでに個人で導入している場合はそのままとして、使用者が新規に導入する場合は会社負担とするケースもあります。通信回線使用料は個人の使用と業務用の使用の切り分けがむずかしいので、一定額を会社負担としているケースが多いようです。
3.電話に関わる費用
会社が貸与するスマホやPHS等は全額会社負担が多く見られます。在宅勤務の場合IP電話を利用する場合、家庭用の電話を流用することが多いため、請求明細などから業務用通話分のみを会社が負担する方法も考えられます。
4.文具、備品、宅配便等の費用
文具や備品については、基本的には会社負担が大半です。文具や備品の通販業者と契約し、自宅に直送してもらい、請求は会社へという方法を採っているケースもあります。切手は前もって在宅勤務社に適当な量を渡しておけば済みます。会社宛の宅急便は着払いの対応でよいでしょう。
5.水道光熱費
電気・水道代金は家庭で使用した分と業務で使用した分を切り分けるのはむずかしいので、在宅勤務手当など定額の経費負担を採用するケースが多く見られます。
テレワークの人事評価制度について
人事評価制度については、在宅勤務の日数や時間により対応が変わります。週に1~2日程度であれば、事業所内での勤務の方が長いため従来の制度で対応することが可能でしょう。
在宅勤務が常態となる場合は、制度の再構築の検討が必要となります。具体的には事業所への出勤が少ないので、プロセスよりも結果(業績)重視の評価へのシフトが考えられます。
この場合、評価制度に対して疑義が抱かれないように、評価制度や賃金制度を再設計しなくてはなりません。同時に在宅勤務を選択する従業員に対して、その内容を詳細に伝える必要があります。併せて就業規則の作成と変更を届け出る必要もあります。(労働基準法第89条第2号)。
在宅勤務が主となる勤務体制の場合、MBO(目標管理制度)が馴染みやすいでしょう。上司と従業員で面接し、目標の設定と共有化をはかります。日々の報告・連絡・相談をより密にして、業務の進捗状況の共有化が必要です。
どちらにせよ、テレワーク制度を利用している従業員が不利にならないような公正明大な評価システムを周知することが重要となります。
従業員の意識改革も必要になる
テレワークの導入前後で、従業の制度では対応しきれない分野が出てくるのは、これまで説明の通りです。制度改変と同時に必要となるのは、社員の意識改革です。育児や介護に関係ない社員や、業務内容上、テレワークが不可能な社員にとってはなぜ一部の社員のために評価制度が変わるのか。今まで問題なく進めてきた現状をなぜ変えなくてはならないのか。このような意識の問題や反発が予想されます。
そこに対する会社としての考え方、社員が働き続けられる環境をなぜ用意したいのかという想いをしっかりと落とし込むことが重要です。
ここをしっかりとクリアにすることで、新しい働き方に対する会社の本気度は社員へ伝わり、制度として浸透していくことでしょう。
連絡体制について
取引先との重大なトラブル、情報通信機器の異常により使用不可能になった場合、地震や台風などの自然災害やパンデミックなど、緊急時の連絡方法と体制についてきちんとした取り決めがBCPの観点からも重要です。異常事態をカテゴリー分けし、それぞれの場合に応じた連絡のルールを策定しておく必要があります。
安全衛生について
在宅勤務者であっても通常の従業員と同様に、健康保持を確保する必要があり、具体的には健康診断(労働安全衛生法第66条第1項)や安全衛生教育の実施をしなくてはなりません。特にテレワークの場合、パソコンやモバイル端末を利用する場面が事業所勤務よりも機会が増えることが考えられるので、留意が必要です。「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(平成14年4月5日基発第0405001号)が公表されているので、内容の周知徹底と、健康管理のための助言が必要です。
労働災害について
在宅勤務であっても、業務が原因となる災害は、労災保険給付が受けられますが、日常生活上の怪我や病気などは対象となりません。業務を起因とするものか、私的行為によるものかをきちんと判断する必要があります。
労災は「業務遂行性」と「業務起因性」の二つの要件が満たされている場合に適用されます。「業務遂行性」とは「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」を言います。「業務起因性」は「業務または業務行為を含めて“労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態”に伴って危険が現実化したものと経験則上認められること」を言います。
従って、テレワークの場合、負傷や疾病が発生した具体的状況により判断されることになります。
おわりに
テレワークの内「在宅勤務」が可能な業務は業種・業態によっては導入が困難として、最初から諦めてしまうケースもあるようです。しかしながら業務を徹底的に分析してみると、月に1回、あるいは週に1回程度なら「在宅勤務」が可能な業務も見つかるはずです。
「在宅勤務」と言うと在宅勤務状態が常態であると勘違いしがちですが、一定の曜日あるいは期間を在宅勤務にあてるという形態でも、業務効率の向上やBCPに有効な場合があります。従業員にとっても、ワークライフバランスを整い生産性が向上したり、介護や育児を行ったりする時間が確保できたりと、有益なワークスタイルとなる可能性も十分あります。
情報セキュリティには注意を払いつつ、ぜひ労務管理を柔軟な思考で前向きに見直し、新たな働き方の導入に挑戦してみて下さい。