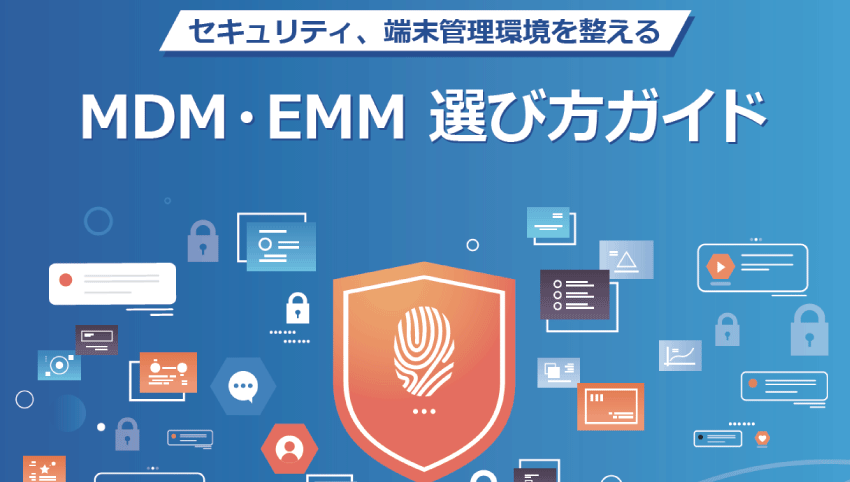業務効率化ツール10選。SFA、CRM、バックオフィスなどの目的別に紹介!

企業にとって業務効率化はコストダウンと生産性向上の両面から経営にインパクトのある、重要なアプローチです。
では業務効率化にはどんな方法があるかと言うと、目的によって様々なアプローチやツールが存在します。
本記事では、以下の効率化目的別に業務効率化を実現するツールにフォーカスしてご紹介します。
・案件管理(営業活動)
・顧客管理(マーケティング活動)
・プロジェクト管理
・コミュニケーション
・バックオフィス業務
目次[非表示]
- 1.案件管理の効率化(SFA)
- 1.1.Sales Cloud
- 1.2.Senses
- 2.顧客管理の効率化(CRM)
- 2.1.HubSpot CRM
- 2.2.kintone
- 3.プロジェクト管理の効率化
- 4.コミュニケーションの効率化
- 4.1.Microsoft Teams
- 4.2.LINE WORKS
- 5.バックオフィス業務の効率化
- 5.1.SAP Concer
- 5.2.HRMOS採用
- 6.業務効率化ツール選定のポイント
- 7.自社に最適なツールの導入に向けて
案件管理の効率化(SFA)
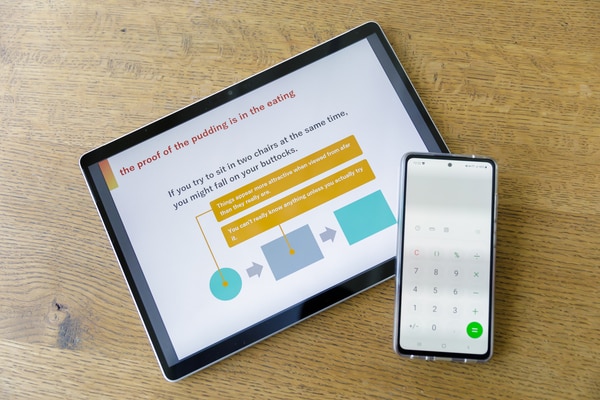
SFA(Sales Force Automation)とは、主に企業のセールス部門の業務を支援するためのシステムを指します。顧客管理機能や案件管理機能、営業成績に関わる予実管理機能などが実装されており、セールスチームの生産性向上と、他チームとの情報連携のために活用されています。
ここでは、Salesforce社が提供する「Sales Cloud」と、株式会社マツリカが提供する「Senses」についてご紹介します。
Sales Cloud
Sales CloudはSFAにおける一般的な機能を網羅しているほか、同社が提供するCRMおよびMAシステムとの連携や、充実したアフターサポートサービスによるリードサポートを実現できます。
また、営業活動を進める上での必要な情報を、ダッシュボード上で一覧で確認できるので、操作性に優れています。特にレポート作成用のオープンAPIを活用し、データをインフォグラフィカルに表現することで、社内に営業活動状況をわかりやすく共有することが可能です。
Senses
Sensesは、サービス継続率98%という実績を誇る国内産SFAシステムで、スタートアップから大企業まで2,300社以上が利用しています。
国内産ということで、充実したカスタマーサポートサービスが特徴となっており、導入支援から運用強化まで、ツールを最大限活用するための支援を行ってくれます。
また、直感的にわかりやすいUI設計になっていることから、現場の営業メンバーにとっては非常に操作性が良く、業務効率化に寄与するツールであると言えます。
▼合わせてよく読まれている資料
顧客管理の効率化(CRM)

CRM(Customer Relationship Management)とは、顧客情報やリード(見込み顧客)管理のためのシステムを指します。顧客とのコミュニケーション履歴や関係情報等を一元的に管理するために活用されています。
ここでは、HubSpot社が提供する「HubSpot CRM」と、サイボウズ株式会社が提供する「kintone」についてご紹介します。
HubSpot CRM
インバウンドマーケティングの概念で有名なHubSpotが提供するCRMシステムでは、顧客や顧客企業情報の管理機能はもちろん、フォーム・リストの作成やマーケティング施策の効果測定等が可能となる機能、Google広告や各種SNS広告への対応機能、SFA機能、さらにはカスタマーサポートを支援するような機能など、非常に充実した機能群を提供しています。
SEO対策に力を入れたい企業や、インバウンドマーケティングに向けたコンテンツの活用を視野に入れている企業にとって、特におすすめのCRMツールとなります。
kintone
サイボウズ株式会社が提供する「kintone」は、自分で業務に合わせたシステムを構築できる、非常に汎用的なCRMツールです。
顧客管理やSFA的な案件管理はもちろん、問い合わせ管理やそのフォーム作成まで、CRM業務に必要なシステムの構築を簡単かつ直感的に進めることができます。
プロジェクト管理の効率化

あらゆる企業では、大小様々なプロジェクトが並行して進んでいることでしょう。そんなプロジェクト管理業務を効率化するDXが複数存在します。
ここでは、株式会社ヌーラボが提供する「Backlog」と、Asana社が提供する「Asana」(読み方:アサナ)についてご紹介します。
Backlog
一般的にプロジェクト管理を進める際には、PMBOK(Project Management Body of Knowledge)で定義されているような様々な領域の知識体系が必要となりますが、Backlogはその中でも「タスク管理」と「情報共有」に焦点を絞ることで、ユーザーがハードル低くツールを利用開始できる仕組みにしています。
メインのタスク管理はガントチャート形式で表現されており、メンバー間でのコミュニケーションやコラボレーションを促進するような機能に力を入れていることから、プロジェクト推進におけるコミュニケーションコストの低減に貢献すると言えます。
Asana
全世界190ヵ国で利用されているというAsanaは、タスク管理に特化したプロジェクト管理ツールです。
「誰が」「どのタスクを」「いつまでに」対応するのかを一覧表示でわかりやすく管理できるので、タスク漏れによるプロジェクトの遅延を防止します。また、日々ルーティン的にこなすようなタスクについてはオートメーション機能と呼ばれる自動処理機能も実装されており、人の手による煩雑な作業を可能な限り軽減するための工夫も随所に散りばめられています。
コミュニケーションの効率化
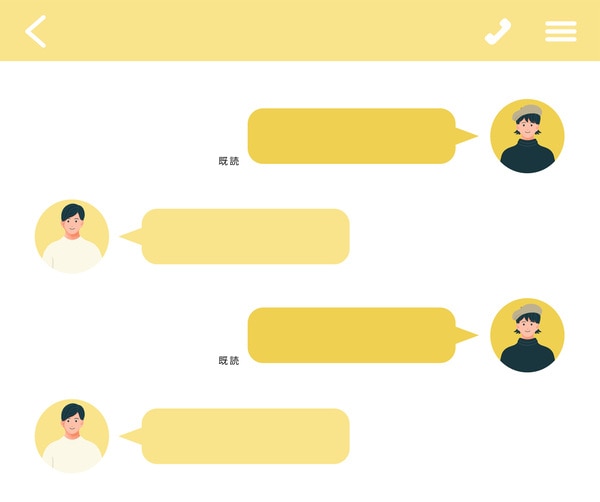
リモートワークの増加に伴い、組織内コミュニケーションの活性化は経営陣にとっての一つの大きなトピックと言えます。
ここでは、Microsoft社が提供する「Microsoft Teams」と、ワークスモバイルジャパン株式会社が提供する「LINE WORKS」についてご紹介します。
Microsoft Teams
Microsoft Teamsは、ビデオ通話機能やストレージ機能など、多様なビジネス用途の機能を有するビジネスチャットツールです。
同社が提供する「Microsoft 365」の一機能として含まれているので、同サブスクサービスを導入している企業であれば、そのままお使いいただけるでしょう。もちろん、Microsoft Teams単独で契約・利用することも可能です。
LINE WORKS
LINE WORKSとは、LINEのようなユーザーインターフェースをもつビジネスチャットツールです。日本ではLINEの普及率が非常に高いので、導入作業はもちろん、メンバーへの普及も非常にハードル低く進めることができる点が、大きな特徴となっています。
日報やアンケートなどの機能も用意されており、様々なシーンで活用できることから、ビジネス向けのアプリケーションとしてセキュリティ面でリスクの低い利用が可能となっています。
バックオフィス業務の効率化

企業のフロントオフィス業務だけでなく、人事や経理などのバックオフィス業務の効率化に向けたツールも多く存在します。
ここでは、SAPグループの株式会社コンカーが提供する「SAP Concer」と、株式会社ビズリーチが提供する「HRMOS採用」についてご紹介します。
SAP Concer
SAP Concerは、経費精算・出張管理・請求書管理ができる経理業務効率化のためのクラウドサービスです。
これまで手作業で行われていた領収書などの入力作業をシステムで一元管理することによって経費生産の自動化を推進し、経理業務のペーパーレスを実現します。
具体的には、法人カード・各種アプリ/キャッシュレス決裁・交通系ICカードと連携や、電子帳簿保存法への対応などの機能が挙げられます。
HRMOS採用
HRMOS採用は、企業の採用活動を効率化するためのHRサービスです。その最大の特徴は、候補者とのやりとりや面接官との日程調整など、煩雑な業務を一つの画面で管理できる点にあります。また、応募経路別および求人別の選考通過率や辞退数などを可視化して、必要に応じてレポート出力することも可能なので、自社の採用分析を強化することも可能です。
採用プロセスにおける候補者の途中離脱や内定辞退などで悩んでいる企業に最適なツールと言えます。
業務効率化ツール選定のポイント

業務効率化ツールの選定には様々な観点が必要ですが、中でも重要なポイントは以下の通りです。
- 導入の目的を明確にする
- 適切なKPI設定
- 自社に必要な要件の洗い出し
- 運営体制の構築が可能かの判断
導入の目的(KGI)が明確にならないと、効果測定のための適切なKPI設定もうまく進みませんので、この2つはセットで考えるようにしましょう。
また、自社に必要な要件は何なのかを、現場と責任者が一緒になって考え、共通認識を持つことも大切です。
さらに、ツールを導入しても運営する体制が整っていなければ意味がありません。運営体制の構築が可能なのかの判断も、選定と並行して進めるようにしましょう。
自社に最適なツールの導入に向けて
最後にお伝えした通り、何よりもまずツール導入の目的を明確にする必要があり、その上で、自社に必要な要件の洗い出しや適切なKPIの設定、運営体制の構築が可能かの判断をした上で導入を進めることが大切です。
業務効率化にも様々な領域とアプローチが存在するので、本記事で言及したツール選定のポイントをクリアした上で、自社に最適なツールを導入しましょう。
▼合わせて読みたいページ