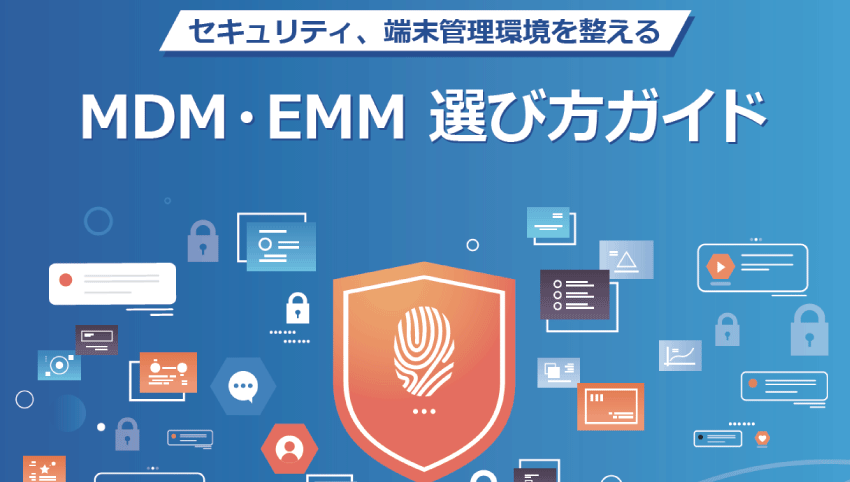情報共有ツールの使用でありがちな失敗とは?効果的な活用事例も紹介!

テレワークの普及により多様な働き方が可能となった一方で、従業員間のコミュニケーションが減り、情報共有の機会も少なくなった企業が増えつつあります。このような状況で従業員間のやり取りを活発化させるためには、情報共有ツールの導入が不可欠です。
しかし情報共有ツールも、ただ導入すれば良いというものではありません。導入したもののメリットを感じない場合は、使用においてありがちな失敗をしている可能性が考えられます。
本記事では情報共有ツールを導入した場合に起きやすいありがちな失敗例と、効果的な活用方法を紹介します。
目次[非表示]
- 1.情報共有ツールのありがちな失敗例
- 1.1.導入したものの使われない
- 1.2.導入後に現場が混乱してしまう
- 1.3.コストと効果が見合わず使い続けられない
- 2.なぜ情報共有がうまくいかないのか
- 3.情報共有ツール活用のポイント
- 3.1.情報共有を行う意義を繰り返し説明する
- 3.2.情報共有ルールを作成する
- 3.3.自社の実態に合ったツールや機能を選ぶ
- 3.4.ある程度自由度の高いツールを選ぶ
- 4.シンプルで使いやすい情報共有ツール2選
- 4.1.Salesforce
- 4.2.LINE WORKS
- 5.情報共有ツールの活用事例
- 6.失敗例を参考に、自社に適したツール選択を
情報共有ツールのありがちな失敗例

情報共有ツールは、業務効率化や生産性向上をサポートしてくれる便利な存在です。導入しても想定したほど効果が得られない場合は、正しく活用されていない可能性があります。情報共有ツールの導入に伴い生じるありがちな失敗は、以下の3つが挙げられます。
■合わせて読みたいページ
導入したものの使われない
情報共有ツールを導入したものの、現場で活用されていないことは珍しくありません。従業員に浸透せず導入しただけで終わったり、一部の決まったメンバーのみが使用していたりするケースです。
情報共有ツールを使用するメンバーが固定してしまうと、そのほかの従業員は従来の方法で情報共有を行うなど導入前と大差ない状態となってしまいます。
導入後に現場が混乱してしまう
企業によっては、情報共有ツールの導入が従業員の負担を増加させている可能性もあります。もともとExcelやビジネスチャット、MAツールなど様々なツールを使用している現場では、新たなツールの追加が従業員の混乱を招くでしょう。デジタルツールだけではなく、アナログツールを多く使用している現場でも同様の問題は生じます。
コストと効果が見合わず使い続けられない
情報共有ツールと一口に言っても、製品やサービスによって料金も利用できる機能も大きく異なるため、導入時は慎重に比較検討して自社に合うものを選ぶことが重要です。知名度や料金、機能の豊富さなどで安易に選ぶと、導入したものの使われない機能が多く、コストのわりには見合った効果が得られず、結果的に短期間で解約する羽目になるでしょう。
なぜ情報共有がうまくいかないのか

企業経営において、情報共有は顧客満足度や売上に影響する要素の1つです。スムーズに情報共有できる体制が整っていれば、たとえば迅速なクレーム処理で問題を小規模なうちに解決できたり、営業担当者が商談中に気付いた潜在ニーズを即座に部署全体で共有できたりと、商機を逃さずに済みます。
重要でありつつも現場で情報共有がうまくいかない原因として、次の3つが挙げられます。
情報共有の重要性が従業員に伝わっていない
従業員が情報共有の重要性を理解していない状態では、積極的にツールを活用してもらうことは困難です。
たとえば顧客情報は、広告配信や商品開発など幅広く役立つ情報でもあります。情報共有によって、様々な部署や担当者が顧客情報を業務に役立てられますが、従業員がその重要性を理解していない場合、個人の営業ノートやPC内のフォルダなどで保管して情報を属人化させかねません。
情報共有ルールが統一されていない
情報共有ツールの導入時に大雑把な指示のみ行うことも、失敗につながる原因です。「営業進捗をツールで共有する」など行うことだけを決めている場合、報告内容やタイミングが従業員ごとに異なり、かえって状況を把握しにくくなる場合があります。
明確なルールがなければ、従業員はそれぞれの方法や自分に合ったタイミングで進捗を報告することになるため、必要な情報が記載されていなかったり、共有自体が遅くなったりと、業務効率の低下を招きます。
自社に適したツールや機能を把握できていない
ツールを導入する際には機能の豊富さに目が行きがちですが、それが必ずしも自社に適した機能とは限りません。
便利な機能を豊富に有していても、自社の状況やニーズに合っていなければ使われず、費用対効果が見込めない結果となってしまいます。
情報共有ツール活用のポイント

情報共有ツールを導入したあとは、従業員に浸透させて活用してもらうことが重要です。前述のありがちな失敗例が当てはまっていると感じる場合は、情報共有ツールの変更を検討する前に、導入後の対策は十分だったかどうかも見直してみましょう。
情報共有を行う意義を繰り返し説明する
大前提として、従業員が情報共有を行う意義を理解しておかなくてはなりません。情報共有によって得られるメリットや、反対に共有せず業務を属人化させると生じるデメリットなどをしっかりと説明しておきましょう。
社内で情報共有に関する勉強会を開催したり、導入に反対する部署や従業員の声に耳を傾けたりして、彼らの不安を解消したりすることも効果的です。
情報共有ルールを作成する
共有される情報を有意義に活用するために、情報共有ルールの作成も必須です。たとえば以下の点をあらかじめ明確化しておくと、報告者以外のメンバーも参照したい情報を効率良く見つけられます。
- いつ報告するか
- 報告すべき項目は何か
- 使用するツールや機能は何か
- 情報の記録方法や保管場所はどうするか
自社の実態に合ったツールや機能を選ぶ
情報共有ツールは国内外で開発・提供されており、機能の数も使い勝手もそれぞれ異なります。ツールを使用する従業員にヒアリングを行うなど、現場で情報共有ツールに求められているポイントを把握したうえで、自社の実態に合ったツールや機能を選びましょう。
たとえば料金面のみを重視すると必要な機能が含まれていなかったり、高いコストをかけて導入したものの使い勝手が悪かったりすると、情報共有ツールは活用されなくなります。
ある程度自由度の高いツールを選ぶ
情報共有ツールは数多く存在しますが、最初から100%満足のいくツールを見つけることは難しいでしょう。そのため一部の機能や使い勝手に妥協して導入するという企業も少なくありません。
長く同じ情報共有ツールを使い続けるためには、ある程度自由度の高いものを選ぶことをおすすめします。既存ツールと連携させたりカスタマイズできたりする情報共有ツールであれば、自社の実態や企業文化に合った方法で活用できます。
シンプルで使いやすい情報共有ツール2選

ここでは、シンプルで誰でも使いやすく、機能も充実しているおすすめの情報共有ツールを2種類紹介します。
Salesforce
「Salesforce」は、米国のセールスフォース・ドットコム社が開発した顧客管理ソリューションです。顧客・案件・自社の状況が一元管理できるため、メンバー全員が効率良く欲しい情報を得られます。
細かいカスタマイズが可能なうえ、コーディングを要しないことも特徴です。そのため複雑な開発作業をせずとも、外部システムとの連携や現場の声を反映した調整を即座に実行でき、自社にとって最適なツールに育てられます。情報共有の方法も手軽で、急を要する報告にもチャットツールで対応可能です。
ツール詳細:Salesforce
関連記事:中小企業の営業改革にSalesforceは必須!メリットと事例を解説
LINE WORKS
「LINE WORKS」は、仕事でも安心して利用できるビジネス版LINEです。基本的には直感的に利用できるため、新しい情報共有ツールの導入に抵抗感を感じる層も、ストレスなく業務に取り入れられるメリットがあります。
Excelなど業務で欠かせないドキュメントの共有もできるうえ、既読メンバーをチェックすることで未読メンバーにリマインドもできるため、従業員同士の連携やコミュニケーションを活発化してくれます。
また、無料プランから有料のプレミアムプランまで、求める機能や予算に応じて4つのプランから選べる自由度の高さも魅力です。
ツール詳細:LINE WORKS
関連記事:テレワークの課題はコミュニケーション不足。解決策はLINE?
情報共有ツールの活用事例

情報共有ツールの選択で迷っているときは、実際に活用している企業の事例を参考にしてはいかがでしょうか。自社と近い悩みを持っている企業が、どのようなツールを導入してどのような効果を得たのか参考にすることで、情報共有ツールに求めるものが見えてきます。
ここでは2社の情報共有ツール活用事例を紹介します。
株式会社ジェイ・シー・エス(Salesforce)
株式会社ジェイ・シー・エスは、エステサロンや美容室に対して信販事務代行やクレジットカード決済などのサポートを行っている企業です。本社のある福岡県を中心に、大阪府や東京都なども合わせて5,000店舗以上にサービスを提供しています。
課題
株式会社ジェイ・シー・エスの事業の根幹を担う営業部と業務部は、きちんとした情報共有システムがないまま業務を行っていたため、必要な情報がスムーズに共有できない課題を抱えていました。日報もExcelで作成しており、過去の情報を参照したいときは営業個人へ問い合わせを行わねばならず、双方の業務圧迫や誤った情報の共有を起こすことも少なくありませんでした。
対策と結果
外部システムの連携やカスタマイズで機能を追加しやすい、Salesforceを導入したところ、属人化していた顧客情報や進捗情報が一元管理できるようになり、誤った情報の共有や進捗の報告漏れを防げるようになりました。
社内SNS「Chatter」も活用され、部門間のコミュニケーションがスムーズに行われるようになり、業務効率化にもつながっています。
事例詳細については、こちらをご覧ください。
あすか製薬株式会社(LINE WORKS)
あすか製薬株式会社は、甲状腺低下症治療薬の市場において95%のシェア率を誇る主力製品「チラーヂン」をはじめ、主に内科・産婦人科・泌尿器科の分野で活躍する製薬会社です。高度な専門知識と倫理観を有するMR(医療情報担当者)の育成にも力を入れるなど、医療提供活動も積極的に行っています。
課題
情報共有をサポートするためにMRへPCや携帯電話、iPadを支給していましたが、営業所内勤者や管理部門、上長との情報共有がスムーズに行われていない状態でした。主な情報共有は電話やメールといったタイムラグや見落としが生じやすい手段で行われており、更にメールではビジネスシーン特有の面倒な前置きが業務効率の低下を招いていました。
対策と結果
面倒な前置きなく直感的に複数人と情報共有できるLINE WORKSを導入したところ、情報周知のスピードが飛躍的に向上しました。
以前は多くの従業員へ連絡事項を送るときは社内ポータルサイトの掲示板を使用していましたが、従業員が情報を確認するまでに時間がかかり、効率的とは言えませんでした。LINE WORKSを導入した現在は端末上に通知が来るため即座に確認しやすく、情報発信からわずか数分で4人に1人が既読状態になるほど効率的に情報共有されています。
失敗例を参考に、自社に適したツール選択を
スムーズな情報共有は、企業の売上を左右する重要な要素です。業務効率化のための施策を検討している方も、現場の実態に合わせた情報共有ツールの導入を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
コネクシオは、企業の情報共有成功のため、各種ツールの導入から実際の運用までトータルでサポートしています。たとえば本記事で事例を紹介した企業は、ツール導入にともない携帯電話からiPhoneへの切り替えも行ったため、モバイル用の総合セキュリティサービス(ISMB)も提案し、安心して情報共有できる環境作りに貢献しました。
企業が抱える課題や現場の実態に合ったツールの提案をしますので、まずはぜひご相談ください。