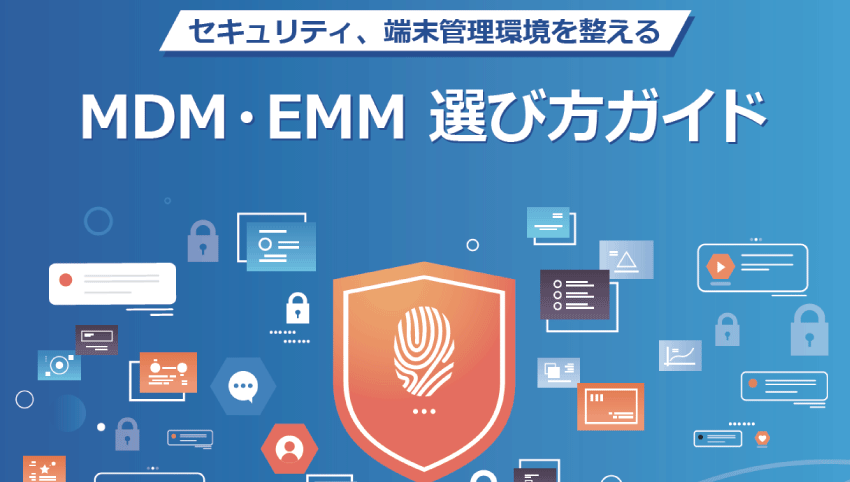インバウンドマーケティングとは?デジタル時代のマーケティング手法をわかりやすく解説

インバウンドマーケティング(Inbound Marketing)とは、潜在顧客や見込み顧客にとって有益な情報を提供することで、関係性を構築し、自社の商品やサービスの顧客まで育成していくマーケティングの概念です。
ひと昔前と比べると、スマートフォンや新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、顧客の消費行動は劇的に変化してきました。デジタルが当たり前となった現在において、消費行動を把握してマーケティング施策を行う必要があります。これまではテレビCMなどマスメディアを活用したアウトバウンドマーケティングが有効とされていましたが、消費行動や購買プロセスの変化に伴い、インバウンドマーケティングを導入する企業が増えています。
現在では、インバウンドマーケティングとアウトバウンドマーケティングを戦略的に使い分けるのが主流で、多くの企業やwebサイトやSNSを通じて多岐にわたるデジタル施策を実行しています。
今回は、インバウンドマーケティングの概要やその効果、手法について解説します。
目次[非表示]
インバウンドマーケティングとアウトバウンドマーケティング
まずインバウンドマーケティングとアウトバウンドマーケティングの違いについて説明します。
アウトバウンドマーケティングは、企業が主体となって消費者に情報を発信していくプッシュ型のマーケティング手法です。テレビCMやダイレクトメール、テレマーケティング、街頭ビジョンや看板、デジタルサイネージなどが挙げられます。
特徴は、不特定多数のマスに向けて情報発信ができるので、興味を持つ潜在顧客にダイレクトにアプローチできます。一方で、コストが高く、興味がない層にも情報を発信することになるので費用対効果を注視する必要があります。
インバウンドマーケティングは、webサイト上でのホワイトペーパー、ニュースなどのコンテンツ配信やSNSでの共有・拡散を通じて、見込み顧客に発見してもらい、興味をもってもらうマーケティング手法です。
企業発信のプッシュ型であるアウトバウンドマーケティングに対して、インバウンドマーケティングは、見込み顧客が自発的に行動して、企業の商品やサービスに触れていきます。
インバウンドマーケティングが注目される背景
インターネットの爆発的な普及とともに、ユーザーの購買プロセスや消費行動は大きく変化しました。ほとんどのユーザーが購買に至る前に必ず検索エンジンやSNS上で情報収集をしたり、口コミをみて検討します。
その結果、企業本位で行われるアウトバウンドマーケティングにユーザーも嫌悪していることもあり、企業は見込み顧客とのタッチポイントを創出するために、様々なコンテンツを制作してインバウンドマーケティングに力を入れるようになりました。
コンテンツマーケティングとの違いとは
インバウンドマーケティングと似た概念に、コンテンツマーケティングがあります。シンプルに説明をすると、インバウンドマーケティングの手法のひとつがコンテンツマーケティングであり、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを通じて、購買意欲を醸成していきます。よりコンテンツに主眼を置いたマーケティング手法と言えます。
インバウンドマーケティングはコンテンツだけに留まらずユーザーに発見してもらうマーケティング施策全体を指しますが、この2つの手法は切り離せない関係性にあります。
▼合わせてよく読まれている資料
インバウンドマーケティングのメリット
次にインバウンドマーケティングのメリットを解説します。
適切な運用ができると費用対効果が高い
インバウンドマーケティングはアウトバウンドマーケティングと比較すると高い費用対効果が見込めます。ただし、適切な戦略や運用体制が非常に重要になり、成否が分けます。
ペルソナ設計やカスタマージャーニーマップの作成はもちろんですが、常に顧客視点の購買プロセスを検討して、施策を打つ必要があります。
マーケティング資産が蓄積する
広告や展示会などは効果が一定期間に限定されることが多いですが、ブログやSNSを継続的に運用することで、制作したコンテンツは資産として蓄積できます。そのため、マーケティング資産を蓄積できることが大きなメリットとなります。
インバウンドマーケティングで可能となる顧客データ基盤の構築
インバウンドマーケティングを行ううえでベースとなるのはwebサイトの環境構築で、自社サイトやオウンドメディアやソーシャルメディアなどが必要となります。
これらを情報提供のメディアと捉え、その中でコンテンツ発信によって集客・顧客化を目的としたコンテンツマーケティングを実施していきます。
環境構築を用意し、潜在顧客・見込み顧客が関心を持っている有益な情報を発信することで、タッチポイントを創出し、訪問者に対してさらなる理解を促し、そして顧客化からファンになるまで一連のマーケティング活動を行えるようになります。
購買プロセスに応じたコンテンツを配信する
こちらが発信したい情報を盛り込んだコンテンツでは、ターゲットとなるユーザーにリーチできません。先述した通り、インバウンドマーケティングは、ユーザーが主体となり「発見してもらう」ことが重要になります。そのため、コンテンツを設計する際には、見込み顧客の購買プロセスに応じた設計が必須となります。
例えば、缶コーヒーを売っている企業が自社商品を認知してもらうには、ターゲットとして「多忙なビジネスマン」に定めると、「ホッと一息入れたい」「休憩中にリラックスしたい」などのニーズがあるので、「休憩中にリラックスする方法」「気分を落ち着ける飲み物」などのコンテンツを配信することで、タッチポイントが生まれるかもしれません。
認知後には、商品をよく理解し、知ってもらうためのコンテンツを用意します。例えば、「●●産の豆を使用している」「▲▲の抽出方法を取り入れている」といったイメージです。その後は、競合商品などと比較・検討というプロセスも考えられるため、価格や提供価値、お客様の声などのコンテンツが重要になります。
今回はコーヒーを例に挙げていますが、基本的な購買プロセスに合わせたコンテンツの考え方はBtoB商材でも同様です。ひとつ異なるのは、案件になるまでの期間が長くなるためより長期的な戦略を立てる必要があります。そのひとつにリードジェネレーションとリードナーチャリングがあります。
見込み顧客を獲得して、ナーチャリングする
BtoBでは、見込み顧客の個人情報を取得する接点をつくります。ホワイトペーパーやウェビナー、メルマガ登録などよりユーザーが知りたいコンテンツを用意し、登録を促すのが一般的です。このように見込み顧客の情報を取得することをリードジェネレーション(見込み顧客の創出)と言います。
リードはすぐに案件化するわけではありません。リード獲得後は、継続的な接点ができている状態ですので、さらに有益な情報を配信して育成をしていきます。これをリードナーチャリングと言います。
このようにインバウンドマーケティングではユーザーの購買プロセスに合わせて、自社の商品やサービスを発見してもらい、知ってもらい、購入してもらうという一連の流れを指します。
マーケティングオートメーションを利用する
インバウンドマーケティングの課題は、継続的なコンテンツ運用の体制と獲得したリードの管理です。
自社サイト、オウンドメディア、SNS、広告などチャネルが増えるとコンテンツの管理も煩雑となります。また獲得したリードに対してどのような内容のメールを打つのか、リードはサイト内でどのような動きをしているのか、営業がアプローチする適切なタイミングはいつか、などインバウンドマーケティングを人的に運用していると多くのリソースを割く必要があります。
そのため現在はマーケティングオートメーション(MA)と呼ばれるツールを導入する企業が増えています。提供されているサービスによって、機能は様々ですが、シナリオや戦略を設計することでリードに対しての適切な施策を自動で管理することが可能です。
本格的なインバウンドマーケティングの導入を検討されている方はぜひ下記の記事もご覧ください。
▼関連する企業事例・ノウハウ情報