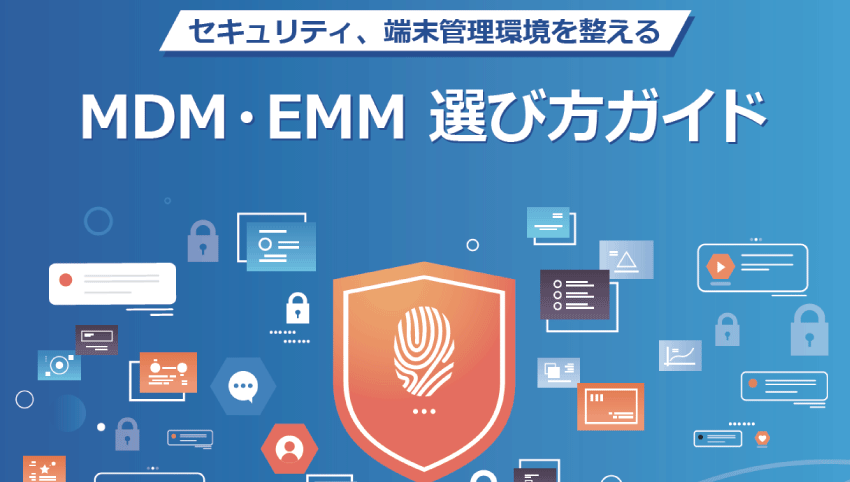EX(従業員体験)を高める。DX・CXとの関係やポイントを紹介

ここ数年でDX(デジタルトランスフォーメーション)への認知・対応は広く普及してきましたが、付随する「EX(従業員体験)」や「CX(顧客体験)」の重要性は未だ不足していると言えます。
特にEXについては、人材不足が顕著になり人材流動性が高まる現代社会だからこそ、会社と従業員の関係は、より長期的な視点でデザインする必要があると言えます。
本記事では、DXやCXとの関連性を説明しつつ、EXの重要性や会社としてEXを高めるためのポイントを解説します。
目次[非表示]
- 1.EX(従業員体験)とは?
- 1.1.EXの要素とは
- 2.EXが注目される背景
- 2.1.EXを高めることのメリット
- 3.DX・CXとの違いと関連性
- 3.1.DXとは
- 3.2.CXとは
- 3.3.EXとDX・CXの関係
- 4.EXを高めるためのポイント
- 4.1.従業員理解を深める(エンプロイージャーニーマップの活用)
- 4.2.EXの高い企業を参考にする
- 4.3.多様なタッチポイントにおけるEX改善を考える
- 4.4.成長プロセスの策定
- 4.5.働き方の柔軟性
- 5.何よりもまずは、自社従業員に対する深い理解から
EX(従業員体験)とは?

EXとは「Employee Experience」の頭文字をつなげた造語で、従業員がその企業で働く上で得られる「体験」の総称を指します。ただし、体験の中でも「満足度」を指すことが多く、一般的には「EXが高い/低い」、つまりは「従業員満足度が高い/低い」という表現がなされることが多い言葉です。
EXの要素とは
EXの要素としては、従業員と企業のあらゆるタッチポイントが考えられます。一例として、以下のような内容がEXの一つと言えます。
入社前の面接、入社時研修、日々の業務、上司/部下や先輩/同僚/後輩等との人間関係、異動、兼務、退職、人事考課などの評価設計、福利厚生、企業文化、報酬体系、スキルアップ機会、課外活動、ワークライフバランスの充実 etc…
これに加えて、「働きがい」や「働きやすさ」など、ワークライフバランスに付随したソフト的な概念についても、EXを構成する要素だと言えるでしょう。
関連資料:あなたの会社は何個当てはまる?コミュニケーション診断から分かる課題解決方法をご紹介
■合わせて読みたいページ
EXが注目される背景

EXが注目される背景には、労働力人口の減少とそれに伴う人材不足、さらには人材の流動性の高まりがあげられます。
特に後者について、かつて終身雇用がメインだった時代と比較すると、現代社会では「転職が当たり前」という就業文化へとシフトしています。また、SNSや口コミサイトなど、転職者や求職者によるUGC(User Generated Contents:ユーザー自身によって作成されたコンテンツ)が増えたことにより、情報の非対称性も着々と解消に向かっています。
このことから企業は、従業員や求職者等との中長期的な関係性の構築が求められており、それゆえに人事部門の役割もHR(Human Resource)の管理からEXの管理へと、その主体が変わってきていると言えます。
EXを高めることのメリット
EXを高めると、以下のようなメリットが期待されます。
- 会社への帰属意識を高める
- 業務効率化と生産性向上の実現
- 働き方改革が進む
これら3点は互いに密接に絡んでおり、「会社への帰属意識が高まる」ことによって、会社としての定着率向上に寄与します。また従業員サイドからボトムアップ型で「業務効率化や生産性向上」の力学が働き、結果として「働き方改革が進む」ことにつながります。
働き方改革については、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:働き方改革とは? 背景と目的、これからの課題。DXとコロナ禍の対応を考える
「新しい働き方」とは? ウィズコロナ時代に求められる打ち手や具体事例、推進のためのポイントを解説
DX・CXとの違いと関連性

ここで、冒頭に記載した「DX」と「CX」とEXの違いについても解説します。
DXとは
DXとは、2004年にスウェーデンのウメオ大学で教鞭をふるエリック・ストルターマン教授が初めて言及したと言われているIT用語です。
そこでは「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と語られたわけですが、その後我が国においては経済産業省が以下のとおり定義しています。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること
DXという単語にさまざまな取組みが内包されていますが、大きくは社内向けDXと対顧客(社外)向けのDXがあります。前者は「守りのDX」と呼ばれ、業務の効率化や業務プロセスの改革などがアクションとして考えられます。また後者は「攻めのDX」と呼ばれており、提供している商品・サービスの提供価値の向上や、ビジネスモデルそのものの変革などがアクションとして考えられます。
なお、DXについては以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:DXやIT活用と生産性向上の関係とは? 指標とともに解説
CXとは
ビジネス界隈でCXと表現するとき、大きくは2つの意味が考えられます。一つは、先ほども出てきた「顧客体験(Customer Experience)」で、もう一つはDXを進める際の視点を組織に落とし込んだ「コーポレートトランスフォーメーション(Corporate Transformation)」です。
どちらもDXと密接に関わる内容ですが、本記事では前者の顧客体験としてのCXについて言及します。
CXの考え方は、もともとマーケティング界隈から醸成されたものです。従来は生産したモノやサービスの機能や性能といった要素で「価値」が図られていたものが、昨今ではそれ以外の要素(購入後のフォロー体制や情報交換可能なコミュニティの有無等)も価値として計られるようになりました。
このような「情緒的な側面」も含めたトータルの価値・UX(ユーザー体験)を重視する必要が出てきたことから、日本語としては「顧客体験」の設計が不可欠になってきたと言えます。
EXとDX・CXの関係
先ほど「DXには守りと攻めがある」とお伝えしましたが、EXとDX・CXの関係を考えると、DXに向けた攻めのアクションが「CX(顧客体験)」であり、一方で守りのアクションが「EX(従業員体験)」と表現できます。
そして、これらは個別に進めるのではなく、互いに循環させながら推進していくことが大切です。顧客体験(CX)を上げるためには、単純に技術やデザインを変えるだけでは十分とは言えず、その提供者である従業員の体験価値(EX)も向上させ、ボトムアップ型でCXを変革する機運を高める必要があります。また、良いCXを提供できれば、そこに対して顧客からの良いフィードバックが社内へと戻ってくるため、EXがさらに高まるという形になります。
このようにCXとEXがポジティブに作用しあい、結果としてDXが推進されるという循環の創出が大切だと言えます。
EXを高めるためのポイント

ここまでの内容を前提に、最後に、EXを高めるためのポイントを5つご紹介します。
従業員理解を深める(エンプロイージャーニーマップの活用)
EXを高めるためには、何よりも自社の従業員理解を深めることが大切です。そのためには、ぜひ「エンプロイージャーニーマップ」を活用しましょう。
エンプロイージャーニーマップとは、従業員が企業と出会ってから退職してOB/OGとなるまでの一連の時間の流れを「マップ」として可視化したものです。マーケティングでCXを高めるためによく活用される「カスタマージャーニーマップ(顧客が商品・サービスと出会ってから購入して活用するまでの可視化したもの)」をEXに応用したものと言えます。
従業員へのヒアリングや評価・出勤状況等の定量データを参考にしながら、従業員がどのタイミングでどのようなことを考えてアクションを起こしているのかを可視化することで、EXを高めるための施策を考える際の強力なツールになるでしょう。
EXの高い企業を参考にする
さまざまな施策を通じてEXが高いと評判になっている企業を参考にすることも大切です。特に、業種業態の異なる企業のケーススタディを進めることで、思わぬ形でEXを高める施策が見つかるかもしれません。
多様なタッチポイントにおけるEX改善を考える
EXの要素の部分でもお伝えしたとおり、EXを高めるためには企業と従業員のあらゆるタッチポイントでの施策が考えられます。入社前時点での施策では、面接前にカジュアル面談を実施してカルチャーフィットの制度を高めることが考えられます。入社後の施策では、たとえば妊活支援や育児支援に関する福利厚生や休暇制度を整えることが考えられます。退職後においても、アルムナイ制度やコミュニティの設計が考えられます。
このように、多様なタッチポイントでEX向上に向けた施策を実行することが大切です。
成長プロセスの策定
EXを高める上で、従業員の「成長」を最大化するための取り組みも重要です。
特に優秀な人材は、成長に貪欲です。自らの能力を高めたいと常に考えていることから、知識やスキルを磨ける教育制度や現場での担当をデザインすることで、自ずとEXも高まることになります。
働き方の柔軟性
自社のビジネスモデルや職種に合わせた働き方の柔軟性も、EX向上に不可欠な要素です。特にコロナ禍を経た現在は、オフィスワークのほかにテレワークやハイブリッドワークなど、企業が従業員による働き方の柔軟性をデザインする傾向が高まっています。
働き方の柔軟性が高まれば、自ずと働くことへのモチベーションも高まり、EXも高まっていくでしょう。
関連記事:ハイブリッドワークとは? 新しい働き方を実現するための注意点・ポイントを解説
モバイルワークとは? テレワークとの違いや導入のメリット、ポイントを解説
何よりもまずは、自社従業員に対する深い理解から
ここまでご覧いただくとお分かりのとおり、EXは「単体のプロジェクトとして実行すれば上がっていく」というものではありません。DXやCXとの三位一体で捉えつつ、継続的に向上させるための体制づくりが大切となります。
まずは、エンプロイージャーニーマップの作成等を通じて、自社で働くあらゆるステークホルダーへの深い理解を進め、その上でEX向上に向けた具体的な施策を考えていきましょう。
■合わせて読みたいページ